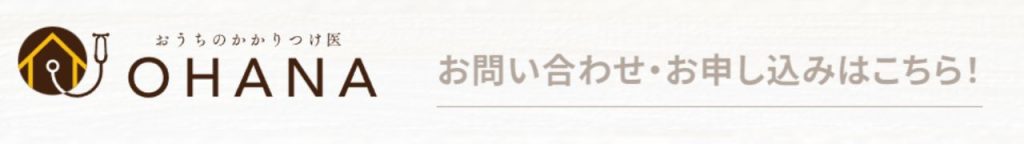お役立ちコラム
和風住宅の木部に適した塗料の種類とは|美しさと耐久性を両立する選び方
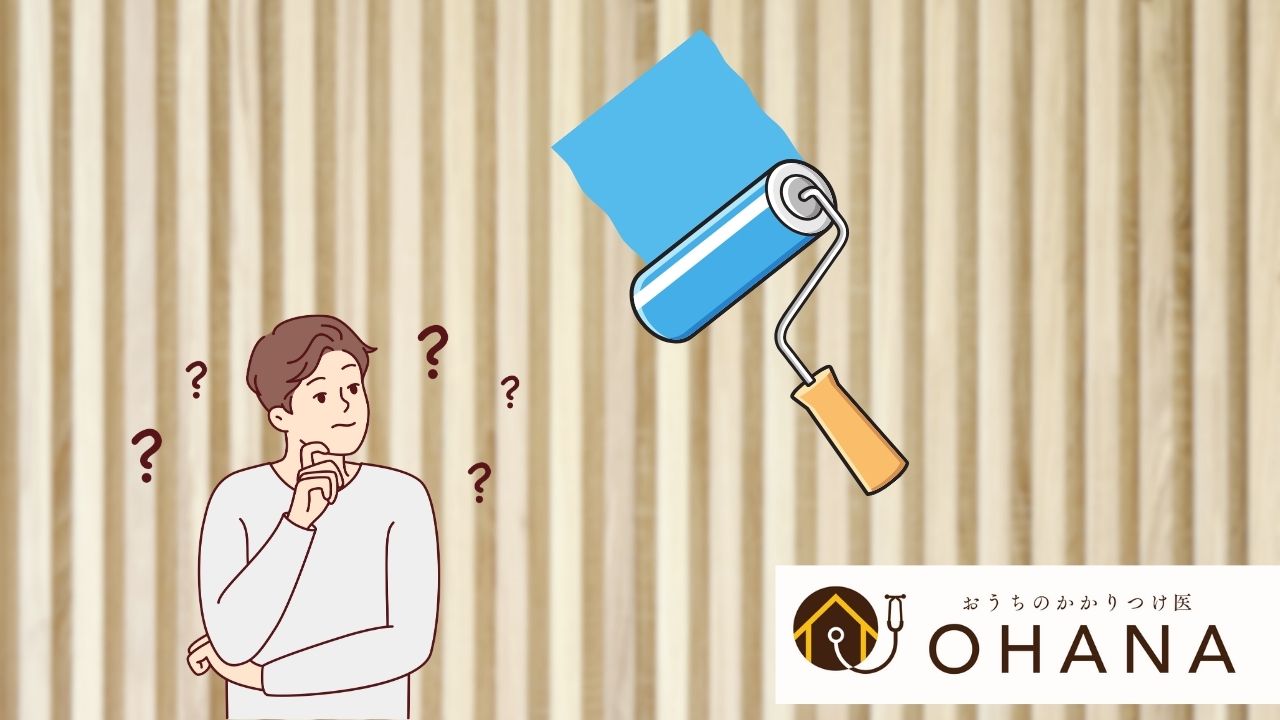
福岡市で外壁塗装工事&屋根塗装&リフォーム工事なら
福岡市城南区の住宅塗装専門店の株式会社OHANA(オハナ)へ!
外装劣化診断士、代表取締役の庄嶋です!
和風住宅の木部は、構造材としての機能性だけでなく、美観や意匠の中心的な存在です。見た目の美しさを活かしながら、紫外線・雨風・湿気といった自然の影響から木を守るには、適切な塗料選びが不可欠です。
今回のお役立ちコラムでは「和風住宅の木部に最適な塗料の種類と特徴」について詳しく解説します。
▼合わせて読みたい▼
福岡市で和風建築の木部塗装を依頼するには|施工の質と業者選びのポイント
和風住宅の木部に求められる塗料の役割

和風住宅の美しさを支えるのが、柱・梁・破風板・戸袋などの「木部」です。天然木の持つ質感や色合いは、塗装やサイディングでは再現できない深みと風格があります。その一方で、木材は紫外線・雨風・湿気など自然環境の影響を強く受ける繊細な素材でもあります。
塗料はその木部を保護し、美観を維持し、耐久性を高めるための不可欠な要素です。単に「色を付ける」だけではない塗料の役割を、まずは整理していきましょう。
外観意匠と保護性能を両立する必要性
和風建築の木部塗装では、「保護」と「意匠」のバランスがとても重要です。木材の自然な風合いを活かすためには、光沢の少ない自然系の塗料が選ばれることが多く、色も木目が透けて見えるタイプが主流です。
しかし、塗料としての機能が弱ければ、数年で木部が劣化してしまい、再塗装が頻繁に必要になるなど、維持管理に手間と費用がかかってしまいます。
美観を保ちつつ、耐候性や防水性もしっかりと発揮できる塗料を選ぶことで、木部は長く安定した状態を維持することができます。つまり、「木の見た目を活かしたまま、しっかり守る」ことが塗料に求められる最大の役割なのです。
自然素材ならではの呼吸性をどう活かすか
木材は呼吸する素材です。湿度が高いときには水分を吸い、乾燥すれば放出する。この調湿性は和風住宅の快適性を支える要素のひとつですが、同時に塗料選びの難しさでもあります。
通気性のない塗料で覆ってしまうと、木の呼吸が妨げられ、内部に湿気がこもりやすくなります。その結果、塗膜の浮き・剥がれ、さらには木材の腐食まで引き起こすことがあります。特に福岡のように湿度が高い地域では、塗膜によって「密閉」するのではなく、木の性質を理解した塗装が求められます。
このため、透湿性に優れた「浸透型塗料」や「自然系オイル塗料」が人気ですが、どれだけ通気性があっても外部環境に弱ければ意味がありません。重要なのは「呼吸を妨げず、かつ外部の侵入を防ぐ」性能を備えた塗料を選ぶことです。
木の種類ごとに異なる塗料との相性
木材とひと口に言っても、使われている樹種によって塗料との相性は異なります。たとえば、杉やヒノキなどの針葉樹は柔らかく吸水性が高いため、浸透型塗料がよくなじみます。一方、ケヤキやナラといった広葉樹は硬くて塗料を弾きやすく、下処理を丁寧にしないとムラになりやすい傾向があります。
また、古民家や築年数の経った和風住宅では、木材が長年の風雨で傷んでいることが多く、その状態によっても塗料の選定は変わります。新しい木材と古材では、吸い込み具合や色の出方が違うため、同じ塗料でも仕上がりに差が出ることもあります。
そのため、業者に依頼する際は「どんな木材か?」「今どんな状態か?」を把握したうえで、塗料の種類を提案してくれるかどうかが、良い業者選びの判断基準にもなります。
▼合わせて読みたい▼
塗料の種類・特徴を知れば比較しやすくなる!塗料選びで失敗しないポイントとは?
木部用塗料の種類と特徴|浸透型・造膜型の違い

木部塗装に使用される塗料には、大きく分けて「浸透型」と「造膜型」という2つのタイプがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、用途や仕上がりの好みに応じて使い分けることが求められます。
浸透型塗料(ステイン・オイル系)の利点と弱点
浸透型塗料は、木の内部に染み込んで内部から保護するタイプです。塗膜を作らないため木の呼吸を妨げにくく、木目を活かした自然な仕上がりになるのが最大の特徴です。和風住宅の外観において、「木の風合いを活かしたい」というニーズにもっともマッチする塗料でもあります。
代表的なものには、天然系オイル(亜麻仁油など)や水性ステイン系塗料などがあり、落ち着いたマットな質感に仕上がります。調湿性も保たれ、漆喰壁や瓦屋根などと調和しやすい点も魅力です。
一方で、耐久性が比較的短いという弱点があり、屋外使用では3〜5年程度での再塗装が必要とされます。また、紫外線にさらされる箇所では色褪せが進みやすく、防水性も造膜型に比べると弱いため、定期的なメンテナンスを前提に選ぶ必要があります。
造膜型塗料(ウレタン・シリコン)の耐久性
造膜型塗料は、木の表面にしっかりとした塗膜を形成し、雨風や紫外線からのダメージを防ぐことに優れています。ウレタン塗料やシリコン塗料などが代表的で、撥水性や耐候性に優れ、7〜10年といった長い耐久性が期待できます。
艶ありや半艶など仕上がりの選択肢も豊富で、「メンテナンス回数を減らしたい」「防水性能を優先したい」という場合に適しています。
ただし、木の質感が隠れてしまいやすいというデメリットもあります。表面が完全にコーティングされるため、木目が見えづらくなり、特有の風合いが損なわれることも。また、塗膜が剥がれた際の補修はやや手間がかかり、DIY向きではありません。
ハイブリッド型塗料という選択肢も
最近では、浸透型と造膜型の特性を両立させたハイブリッド型塗料も登場しています。これは木の内部に浸透しつつ、表面にも薄い保護膜を形成するタイプで、木目を活かしながら耐候性を高めたいというニーズに応える新しい選択肢です。
代表的な製品には、水性浸透保護塗料+紫外線カット機能を備えたものや、微粒子樹脂を含んだ防水型オイルステインなどがあり、用途や好みに応じた調整が可能です。
ただし、製品によっては施工がやや難しい場合もあり、乾燥時間や重ね塗りのタイミングを誤るとムラになることも。業者による施工を前提にするか、十分に製品特性を理解したうえで選ぶのが望ましいでしょう。
▼合わせて読みたい▼
福岡市で和風建築の木部塗装を依頼するには|施工の質と業者選びのポイント
木部を長持ちさせるための成分と機能性

塗料は色や艶だけで選ぶものではありません。特に和風住宅の木部は、雨風や紫外線に長期間さらされるため、「どんな機能を持った塗料か」が耐久性を大きく左右します。防腐・防カビ・防蟻など、見落としがちな成分や処理の違いに注目することで、木部の寿命を大きく伸ばすことができます。
防腐・防カビ・防蟻効果は必要か?
木材は、湿気や雨によって腐りやすく、カビや虫害の被害も少なくありません。これを防ぐためには、塗料に含まれる防腐剤・防カビ剤・防蟻剤といった添加成分の有無を確認することが大切です。
- 防腐成分:木の内部に入り込み、菌類の繁殖や腐敗を抑える効果があります。とくに軒下や地面近くの木部には有効です。
- 防カビ成分:表面に黒カビ・青カビが定着するのを防ぎ、美観を長く保ちます。湿度の高い福岡では特に重要です。
- 防蟻成分:シロアリなどの害虫から木材を守ります。構造材に近い部分や縁側・束柱などに使用することで、建物全体の耐久性にも貢献します。
こうした効果を含む塗料は「防腐・防カビ塗料」として販売されていますが、成分が強すぎると木の色味が変化する場合もあるため、使う箇所に応じて選ぶことが重要です。
含浸タイプ vs 表面被膜タイプの使い分け
木部保護の方法には、「含浸(がんしん)タイプ」と「表面被膜タイプ」があります。どちらにも一長一短があるため、場所によっての使い分けが理想的です。
- 含浸タイプ:浸透型塗料の一種で、木の内部まで成分が入り込み、内側から防腐・防蟻・防カビ効果を発揮します。木の呼吸性を損なわず、自然な仕上がりが得られますが、耐候性はやや劣ります。
- 表面被膜タイプ:造膜型塗料に代表される方法で、塗膜がしっかり形成されるため雨風や紫外線には強いですが、木の呼吸が妨げられることもあるため、定期点検が欠かせません。
屋外で常に風雨にさらされる場所には被膜タイプ、軒下や通気性のある場所には含浸タイプなど、環境に応じた選択がポイントです。
塗装前の処理で耐用年数は大きく変わる
どんなに高性能な塗料を選んでも、下地処理が甘ければ効果は半減してしまいます。木部塗装では「塗る前の準備」がもっとも重要とも言われており、ここを丁寧に行えるかどうかが、仕上がりと耐用年数に直結します。
具体的な前処理の例は以下の通りです。
- 旧塗膜の除去(ケレン作業)
- 表面のカビ・汚れ落とし
- 研磨による毛羽立ち処理
- 防腐・防蟻材の含浸処理(必要に応じて)
また、木材の含水率が高すぎると塗料がはじかれたり、乾燥不良で塗膜にムラが出たりするため、含水率のチェックも業者の腕の見せどころです。
信頼できる施工業者であれば、これらの工程を見積書や説明の中で明示してくれるため、依頼前には「どんな前処理を行うか」を確認しておくとよいでしょう。
▼合わせて読みたい▼
福岡市で和風建築の外壁塗装を依頼するなら|美観と耐久性を守る専門業者の選び方
木部塗装の塗料選びも「おうちのかかりつけ医OHANA」におまかせください!
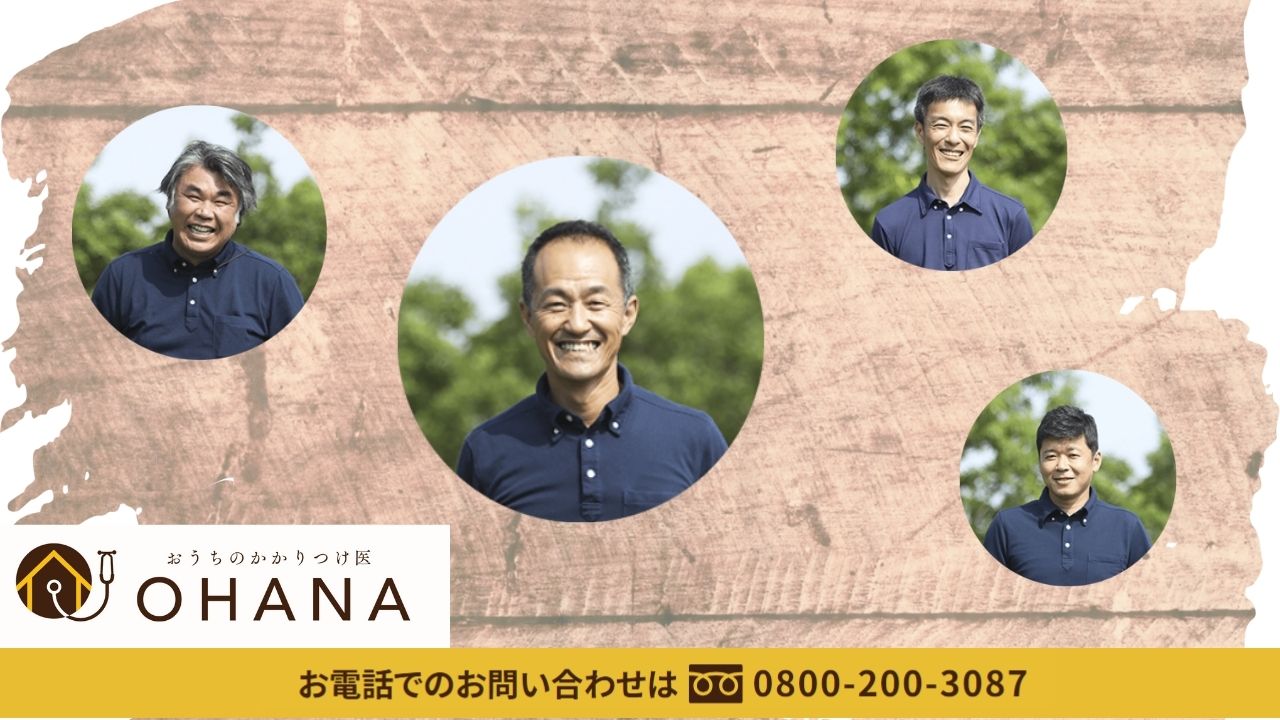
和風住宅の木部塗装には、素材の呼吸性を活かしながら、紫外線や湿気からしっかり守れる塗料を選ぶことが重要です。塗料には浸透型・造膜型・ハイブリッド型など多様な種類があり、それぞれ木の種類や使用環境に応じて適した選択が求められます。
「木目を活かしたい」
「耐久性を重視したい」
「防腐・防カビ対策もしておきたい」
など、目的に応じた塗料の見極めには専門的な知識が必要です。
さらに、塗装前の下地処理や木材の状態確認も、塗装の仕上がりと寿命を左右する重要な工程です。
おうちのかかりつけ医OHANAでは、和風住宅の木部に関する知見と施工経験を活かし、最適な塗料選びと丁寧な施工をご提案いたします。塗料の種類に迷ったときや、ご自宅の木部の状態が気になるときは、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせはフォーム・メール・お電話、またはショールームへのご来店でもお受けしております。お気軽にお声がけください。
お問い合わせ・お申し込みはこちら!
日本の住宅は他の先進国に比べ住宅の耐久年数が
著しく低いと言われております。
特に、お家の防水に関しては定期的なメンテナンスが必要です。
屋根・外壁の塗り替え工事のご相談はオハナへお任せください!!
『オハナ』とは、ハワイ語で家族・仲間という意味です。
家族のように親身にご対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください!