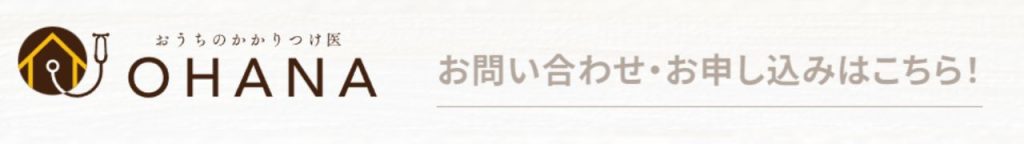お役立ちコラム
和風住宅の外壁塗装|耐用年数はどれくらい?素材と塗料で変わる耐久性とメンテナンス

福岡市で外壁塗装工事&屋根塗装&リフォーム工事なら
福岡市城南区の住宅塗装専門店の株式会社OHANA(オハナ)へ!
外装劣化診断士、代表取締役の庄嶋です!
自然素材の魅力を活かした和風住宅。その美しさを長く保つには、適切なタイミングでの外壁塗装が欠かせません。とはいえ「どのくらいで塗り替えるべき?」「どんな塗料を使えば長持ちするの?」といった疑問を持つ方も多いはずです。
耐用年数は素材や塗料の種類によって大きく異なり、メンテナンスの仕方によっても寿命は延ばせます。
今回のお役立ちコラムでは「和風住宅の外壁塗装における耐用年数と適切なメンテナンス」について解説します。
▼合わせて読みたい▼
福岡市で和風建築の外壁塗装を依頼するなら|美観と耐久性を守る専門業者の選び方
和風住宅に使われる外壁素材とその耐用年数

和風住宅の外壁は、見た目の美しさと素材の質感を大切にするため、洋風住宅とは異なる自然素材が使われることが多くなります。その代表格が漆喰、木材、土壁、モルタルなどの無機系素材や、板張りなどの伝統的な意匠を活かした外装材です。
こうした素材はそれぞれに耐久性の特性があり、メンテナンスの方法や塗装のタイミングを見誤ると、本来の耐用年数を大きく下回ってしまう可能性があります。どの素材がどれくらいもつのか、あらかじめ把握しておくことで、適切な管理ができるようになります。
漆喰や木部の耐久性と劣化の進み方
漆喰は和風住宅を象徴する外壁仕上げのひとつで、調湿性や防火性に優れた素材です。一般的に漆喰の耐用年数は「10〜15年程度」とされていますが、日当たりや風雨の影響、施工の精度によってはそれより早く劣化する場合もあります。
ひび割れやチョーキング(表面が白く粉をふく現象)が見られたら、表面の保護機能が落ちてきているサインです。
木部については、無垢材や板張りの外壁に使われるケースが多く、塗装の種類によって耐久性が大きく変わります。未塗装のままでは数年で色あせや腐朽が進行しますが、防腐塗料や木材保護塗料を定期的に塗り直すことで10〜20年程度の耐用年数が期待できます。
ただし、紫外線に弱いため、南側の外壁では特に劣化が早まりやすい点に注意が必要です。いずれの素材も、使用環境によってコンディションに差が出やすく、定期的な点検によって状態を把握することが長持ちの秘訣になります。
土壁・モルタル・板張りの寿命はどれくらい?
土壁は、古民家などに見られる伝統的な壁材で、藁や土、砂などの自然素材を混ぜて塗り固める仕上げです。耐久年数は「20〜30年」とも言われますが、これはあくまで構造自体の寿命であり、表面の美観や保護機能を維持するには定期的な塗装や補修が必要です。湿気に弱いため、塗装による防水対策が特に重要です。
モルタル外壁は、セメントと砂を混ぜた素材で、和風・洋風問わず幅広く使用されています。塗装で保護することで「10〜15年」の耐用年数を保つことが可能ですが、ひび割れや浮きが出やすいため、塗装だけでなく下地の補修が重要になります。
板張りは、木材を外壁として使う仕上げ方法で、見た目にも重厚感があり和風住宅に多く採用されています。塗料の種類とメンテナンス頻度に大きく左右されますが、表面保護が適切に行われていれば「15〜20年程度」の耐用年数が見込めます。ただし、隙間からの水分侵入には弱く、シーリングや塗膜の劣化チェックが欠かせません。
素材に合った塗装をしないと寿命が縮む理由
和風住宅に使われる自然素材は、いずれも「呼吸する壁材」と言われるように、湿気を吸収・放出する性質があります。そのため、一般的な洋風住宅に使うような密閉型の塗料を用いると、内部に湿気がこもってしまい、かえって素材の劣化を早めてしまうことがあります。
たとえば、木部には浸透性のある自然系塗料や防腐塗料が適しており、漆喰やモルタルには透湿性の高い塗料を選ぶことが理想的です。見た目だけで塗料を選んでしまうと、早期に塗膜が剥がれたり、下地にカビが発生するなど、思わぬトラブルに繋がるリスクがあります。
また、素材ごとに必要な下地処理の方法も異なります。たとえば、漆喰の上からそのまま塗料を乗せてしまうと、密着不良による剥離が起こる可能性があるため、専用の下塗り材を使用する必要があります。板張りや木部も、下地の研磨や防虫処理など、細かい工程を省かずに行うことで、ようやく本来の耐用年数に到達します。
外壁塗装の耐久性は、塗料の性能だけでなく、「素材に対する理解」と「丁寧な施工」があってこそ発揮されるものです。和風住宅にふさわしい塗装を選ぶことが、結果として建物全体の寿命を延ばすことにつながります。
▼合わせて読みたい▼
和風住宅の外壁塗装はいつがベスト?劣化を見逃さない適切なタイミングとは
塗料の種類と施工方法で変わる耐用年数

外壁塗装の耐用年数は、外壁材の種類だけでなく、使用する塗料のグレードや施工の仕方によっても大きく変わります。とくに和風住宅は自然素材が多く、塗料との相性が仕上がりや耐久性に直結します。
「見た目が好みだから」「安いから」といった理由で塗料を選んでしまうと、せっかくの塗り替えが数年で剥がれてしまうことも。長く快適に暮らすためには、目的に合った塗料と、確かな技術での施工が不可欠です。
主な塗料(アクリル・ウレタン・シリコン・フッ素)の耐用目安
塗料にはグレードがあり、それぞれに期待される耐用年数が異なります。一般的な塗料の種類と目安となる耐久年数は以下のとおりです。
- アクリル塗料:5〜7年
比較的安価で手軽に塗装できるものの、耐久性は低め。和風住宅には不向き。 - ウレタン塗料:7〜10年
柔軟性があり、木部など動きのある素材にも比較的対応可能。ただし紫外線にやや弱い傾向がある。 - シリコン塗料:10〜15年
価格と性能のバランスがよく、最もよく使われている塗料のひとつ。透湿性のあるタイプなら漆喰やモルタルにも相性が良い。 - フッ素塗料:15〜20年
高耐久・高機能で、長期的にメンテナンス回数を減らしたい方に向いている。価格は高めだが、トータルコストで考えれば有利になるケースも。
耐用年数はあくまで目安であり、実際には使用環境や外壁材との相性、施工精度によって差が出ます。長寿命な塗料を選べば安心というわけではなく、適材適所の選定がポイントです。
和風建築に多い木壁には「キシラデコール」がオススメ
キシラデコールは、大阪ガスケミカルが製造・販売する木材保護塗料で、屋外木部の耐久性と美観を保つために広く使用されています。その特徴は、木材に深く浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮する点にあります。これにより、塗膜の剥がれや膨れが起こりにくく、木材の呼吸を妨げずに通気性を保つことができます 。
また、キシラデコールは日本の気候に適した耐候性を備えており、紫外線や風雨から木材を守ります。さらに、作業性にも優れており、塗装工程が簡単で、DIY初心者でも扱いやすい点が魅力です 。
カラーバリエーションも豊富で、ピニー、チーク、エボニ、カスタニ、タンネングリーン、マホガニ、パリサンダ、シルバグレイ、オリーブ、ウォルナット、ジェットブラック、ワイス、スプルース、ブルーグレイ、カラレス(無色)など、多彩な色合いから選ぶことができます 。
キシラデコールは、ウッドデッキ、フェンス、ログハウス、ガーデン家具など、さまざまな屋外木部に適しており、長期的な保護と美観の維持に貢献します。その信頼性と実績から、プロの施工業者だけでなく、一般のユーザーにも広く支持されている塗料です。
和風住宅に合う塗料選びのポイント
和風住宅の外壁は、木材や漆喰など、呼吸性のある素材が多く使われています。こうした素材には、通気を妨げない透湿性のある塗料が必要です。密閉性の高い塗膜を形成してしまうと、内部に湿気がこもり、塗膜の膨れや素材の腐朽を招く恐れがあります。
たとえば、木部には「浸透型塗料」や「自然系オイル塗料」などが好まれ、木目を活かしつつ素材そのものを保護する役割を果たします。
一方、漆喰にはシリコン系のつや消し塗料や、専用の漆喰風塗料などが適しています。艶のある仕上がりは和風の意匠に合わないことが多く、マットな質感で景観に溶け込む塗料が選ばれる傾向にあります。
「高耐久=高相性」ではないという点に注意が必要です。いくらフッ素塗料が長持ちしても、素材に合わなければ逆効果になることもあります。選定の際は、価格や年数だけでなく、外壁材との相性や意匠への配慮も加味した判断が大切です。
下地処理や塗り重ねで差が出る耐久性
塗料の性能を最大限に引き出すには、「どんなふうに塗るか」が非常に重要です。下地処理を怠ったまま塗装を行えば、どんなに高性能な塗料を使っても数年で剥がれてしまう可能性があります。
たとえば、旧塗膜の劣化が激しい場合は、ケレン(研磨)でしっかりと汚れや浮き部分を除去する必要があります。ひび割れがあれば補修材で埋め、シーリングの劣化箇所は打ち替える。こうした工程を丁寧に行うことで、塗料の密着性が高まり、耐久性も向上します。
さらに、塗装は「下塗り・中塗り・上塗り」の3回塗りが基本です。下塗りで密着性を高め、中塗りと上塗りで塗膜の厚みと保護性能をつけていくことで、塗料が本来の性能を発揮します。実際には塗り回数を減らしてコストを下げようとする業者もあるため、契約時には「何回塗るのか」「下地処理はどこまで行うか」といった内容を確認することが大切です。
和風住宅の塗装は、見た目の仕上がりだけでなく、長期的な耐久性を左右する作業です。手を抜かず、丁寧な施工がなされているかどうかが、数年後の違いとして現れてきます。
▼合わせて読みたい▼
超低汚染塗料や親水性塗料で塗装すると外壁や屋根の汚れが目立ちにくくなる!メリットや塗料の選び方とは?
長持ちさせるために必要なメンテナンス習慣

外壁塗装は一度終わったら終わりではありません。特に和風住宅のように自然素材を活かしている建物は、経年による変化が出やすいため、施工後のメンテナンスによって耐用年数が大きく左右されます。
こまめな点検や早めの補修を行うことで、塗装の寿命だけでなく建物そのものの劣化も抑えることができます。日常的にできることからプロによる点検まで、長持ちさせるための習慣を見直してみましょう。
定期点検は何年ごと?どこを見ればいい?
外壁塗装の後、2〜3年ごとを目安に簡易的な点検を行うのが理想的です。点検といっても専門的な知識は不要で、建物の周囲を歩きながら目視で確認するだけでも十分効果があります。見るべきポイントは以下の通りです。
- 木部の色あせやひび割れが出ていないか
- 漆喰部分に白い粉(チョーキング)が付着していないか
- 塗膜の浮き・剥がれが起きていないか
- カビ・藻・コケが発生していないか
- 雨染みや雨垂れ跡が残っていないか
これらは塗膜の劣化や防水性の低下を示す兆候であり、早期に発見すれば補修のみで対応できる可能性もあります。特に木部は紫外線や雨に弱いため、南面・西面などの日差しの強い方角を重点的にチェックすると良いでしょう。
また、台風や大雨の後など、天候の変化が大きかったタイミングでも一度確認しておくと安心です。
小さな劣化のうちに補修する重要性
外壁の劣化は、初期段階では非常に小さな変化として現れます。たとえば、「ちょっとしたヒビ」や「色のムラ」「薄い雨染み」などは、放置していてもすぐに問題になるわけではありません。
しかし、そこから数ヶ月〜数年の間に劣化が進行し、最終的には塗膜の剥がれや素材自体の腐朽につながってしまいます。早めに補修を行えば、全体の塗り直しを先延ばしにできる可能性もあり、費用面でも大きな差が出てきます。
特に和風住宅は細部の意匠が重要なため、一部の劣化でも全体の印象を損なってしまうことがあります。
補修はDIYでも可能なケースがありますが、木部や漆喰などの自然素材は扱いが難しく、逆に傷めてしまうこともあるため、プロに相談するのが無難です。地域密着型の塗装業者や建築士に年1回ほどの点検を依頼し、必要に応じて部分補修を依頼するというのが理想的な流れです。
塗装以外にもできる耐用年数の延ばし方
外壁塗装の耐用年数は、塗膜の状態だけでなく、住宅全体の環境によっても変わってきます。たとえば、以下のような日常の工夫によって、外壁に与えるダメージを減らすことができます。
- 雨樋の掃除を定期的に行い、外壁への水はねを防ぐ
- 木の枝や葉が外壁に触れないよう剪定する
- 風通しを良くし、湿気がこもらないようにする
- 室外機や荷物を外壁に密着させない
こうした細かな配慮は見落とされがちですが、塗装の劣化原因を減らすという意味では非常に効果的です。特に和風住宅は軒の出が深く、通気性が高い構造が多いため、自然環境とどう付き合っていくかが耐久性を左右します。
また、築年数が20年を超えると、外壁だけでなく下地の劣化も視野に入れて、断熱材や通気層の点検を行うことも検討すべきタイミングです。外壁塗装を単なる「見た目の塗り替え」ではなく、住宅全体の保守・管理の一環として捉えることで、住まいの寿命をさらに伸ばすことができます。
▼合わせて読みたい▼
塗装とカバー工法のどちらを選ぶかは「劣化症状・屋根材・コスト」で異なる!両者の概要・メリット・デメリットもお話しします!
和風住宅の寿命を延ばす外壁塗装とは?「おうちのかかりつけ医OHANA」にご相談ください

和風住宅は、自然素材ならではの風合いや落ち着いた佇まいが魅力ですが、だからこそ外壁塗装には繊細な配慮と専門的な知識が必要です。漆喰や木部、土壁、板張りといった素材は、それぞれに適した塗料とメンテナンス方法を選ばなければ、耐用年数を十分に引き出すことはできません。
塗料の選定ひとつで10年先の状態が大きく変わります。たとえば、木部には通気性を妨げない浸透型塗料、漆喰には透湿性のあるマットな塗料を選ぶなど、素材との相性を踏まえた判断が必要です。また、丁寧な下地処理や塗り重ねといった施工の精度も、耐久性を大きく左右します。
おうちのかかりつけ医OHANAでは、和風住宅の外観美を守るだけでなく、素材を長持ちさせるためのメンテナンス提案を行っております。施工後の点検・補修などアフターサポートも充実。初めての方にも安心してご相談いただける体制を整えています。
長く住み継ぐための外壁塗装、まずは「おうちのかかりつけ医OHANA」に、お問い合わせフォーム・メール・お電話・ショールームへのご来店にて、お気軽にご相談ください。自然素材と共に歩む住まいを、確かな塗装で支えます。
お問い合わせ・お申し込みはこちら!
日本の住宅は他の先進国に比べ住宅の耐久年数が
著しく低いと言われております。
特に、お家の防水に関しては定期的なメンテナンスが必要です。
屋根・外壁の塗り替え工事のご相談はオハナへお任せください!!
『オハナ』とは、ハワイ語で家族・仲間という意味です。
家族のように親身にご対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください!