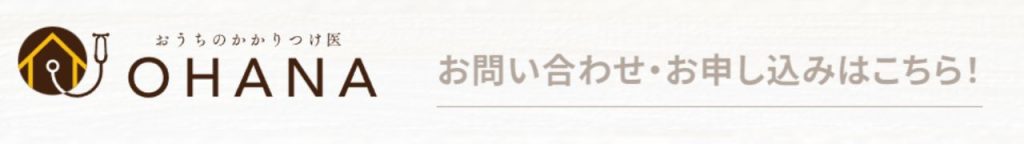お役立ちコラム
建築基準法改正を簡単解説!リフォームや新築への影響を徹底解説

福岡市で外壁塗装工事&屋根塗装&リフォーム工事なら
福岡市城南区の住宅塗装専門店の株式会社OHANA(オハナ)へ!
外装劣化診断士、代表取締役の庄嶋です!
おうちのかかりつけ医OHANAまでお気軽にご相談ください。
令和7年4月に建築基準法改正が施行されます。省エネ基準の適合の義務付けや構造規制の合理化といったさまざまな点で変更があるのです。
ただ、建築基準法が改正される、変更点がわかっても、具体的にどのような変更があるのか理解はむずかしいでしょう。また、一般の方も、住まいやリフォーム計画でどのような影響があるのか、知りたいと思うのではないでしょうか。
そこで今回のお役立ちコラムでは、建築基準法改正について概要を簡単にお話しします。リフォームや新築にどのような影響があるのか?法改正の背景とは?変更点とは?注意すべきポイントは?など、深く掘り下げました。今後の建築計画のためにご参考にしてください。
| ▼合わせて読みたい▼ |
建築基準法改正は「省エネ」と「安全性」の向上がポイント

そもそも、なぜ建築基準法改正が行われるのでしょうか?その背景についてまずはお話しします。
建築基準法改正の目的とは?
建築基準法は、日本国内で建築物を建設したり、リフォームや解体をしたりする場合に守らなければならない、基準や規制するための法律です。建築基準法の目的は、建物の安全性や衛生や、環境を守るための法律といえます。
建築基準法は多種多様な建築物が対象範囲です。一般の住まいとともに、オフィスビルや工場や商業施設など幅広い建物に影響します。その目的は、脱炭素社会の実現です。また、日本では2050年までの「カーボンニュートラルの達成」を目標としています。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を、全体としてゼロにすることです。温室効果ガスとは、たとえば二酸化炭素があげられます。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡2030年には2013年を基準として比較し、温室効果ガスの46%削減することが目標です。
なぜ改正が必要だったのか?その背景とは?
1850年〜1900年の工業化依然と2020年時点とを比較すると、世界の平均気温は約1.1度上昇したといわれています。また、一時の現象ではなく状況を放置しているとさらに気温が上昇すると考えられているのです。
日本の平均気温も変動しながらも上昇傾向にあります。100年のスパンで見ると日本では1.30度の割合で上昇しているのです。とくに1990年代以降で高温傾向が顕著になっています。
カーボンニュートラルの実現は世界中の誰もが取り組むべき課題
カーボンニュートラルの実現は一部の人だけの努力だけでは達成できません。誰もが主体性を持って取り組むべき課題です。もしカーボンニュートラルに取り組まなければ、気候変動という形で表に出ているといわれています。
たとえば、豪雨や猛暑のリスクがあげられるでしょう。この状況で起こり得る問題は、深刻な内容ばかりです。自然災害をはじめ、自然の生態系、水資源、健康や経済活動などさまざまな問題を引き起こします。地球は人間がまともに住めなくなるどころか、生きられない環境になりかねません。そのために、カーボンニュートラルの実現は注目されているのです。
建築基準法改正の具体的な変更点

令和に入ってから、建築基準法改正は令和4年6月17日に交付されました。省エネ基準の適合義務化に併せた木造戸建て住宅建築の際の、建築確認手続きの見直しです。
また、住宅の省エネ改修に対して、住宅金融支援機構による低利融資制度などが施行されました。さらに令和5年4月1日には住宅トップランナー制度拡充や、最高規制等の合理化などが施行されたのです。
令和6年4月1日には、建築物の販売や賃貸の際の省エネ性能表示や、再エネ利用促進区域制度が施行されました。そして令和7年4月の施行に至ります。では、どのような改正内容になっているのかくわしくお話しします。
令和7年施行の建築基準法改正の内容

ではどのような点が改正されるのでしょうか?いくつかピックアップしてお話しします。
省エネ基準の義務化
すべての新築住宅や非住宅に、省エネ基準適合を義務付けることになります。非住宅とは、住宅以外の建築物のことです。たとえば工場、事務所や店舗、大型倉庫などが当てはまります。
改正前は非住宅と住宅に対し、300㎡未満の小規模な建物は、説明義務でかまいませんでした。また、中規模、2,000㎡の大規模な住宅では届け出義務だけだったのです。改正後は、非住宅、住宅をはじめ、大規模でも小規模でも適合義務が求められます。
建築確認の際、構造安全規制などの適合性審査と一体的に実施されているのです。さらにより高い省エネ性能への誘導もされます。たとえば、住宅トップランナー制度です。住宅トップランナー制度は、省エネ性能の底上げを目的としてすでに施行されています。
改正前、対象は大手住宅事業者でした。大手住宅事業者は、規格住宅を大量に供給でき、性能も効率的な向上ができます。そのような大手住宅事業者に対し、市場での流通より高い省エネ性能目標を掲げ、達成するための取り組みを促すものです。
現行では建売・戸建て・注文戸建て・賃貸アパートを対象としていましたが、分譲マンションも追加されます。さらに、販売や賃貸の広告に対して、省エネ性能の表示方法を国が告示することも加わりました。必要に応じて、勧告や公表や命令も含まれています。省エネ性能表示の推進を目的とするものです。このような取り組みにより、高い省エネ性能への誘導を図ります。
再エネ設備の導入促進
促進計画も含まれています。市町村を対象に、地域の実情に応じた太陽光発電等の、再エネ設備や設置促進地域を設定しようという取り組みです。
区域の決定は、住民の意見を聞いた上で設定されています。たとえば、太陽光発電・太陽熱利用・地中熱利用・バイオマス発電などです。また、建築士から建築主に対し、再エネ設備の導入効果等を書面で説明しなければなりません。条例で定める用途や規模の建築物が対象です。この説明に関しては、再エネ導入効果の説明義務として義務化されます。さらに促進計画に即した、再エネ設備を設置する場合、形態規制の合理化として特例許可も創設されました。新築も対象です。
高さ制限や容積率制限、建ぺい率制限の特例許可制度が当てはまります。たとえば太陽光パネルを屋根とした自動車車庫を考えてみてください。建築面積や床面積の他、高さに参入されるものです。従来は認められませんでした。ただ、法改正によって変わります。「太陽光パネルが高さ制限を超える」「建築物本体の影から影を増やさないこと・敷地外に影を落とさないこと」それが確認できれば、特定行政庁から許可が出ます。
建築確認や検査対象の建築物規模等の見直し
木造建築物について、建築確認検査や審査省略制度の対象が見直されます。改正後は非木造と同様の規模となりました。さらに、建築確認審査の対象の大規模修繕や模様替えについては、建築確認手続きが求められます。
また、小規模な伝統的木造建築物は、構造設計一級建築士による設計と確認が必要です。ただし、建築主が専門的知識を持っている場合、建築確認審査を行う場合、構造計算適合性判定は不要となります。
たとえば、改正前は都市計画区域内、階数3以上または延べ面積500㎡以上、都市計画区域街は階数3以上でした。または延べ面積500㎡以上が建築確認審査の対象です。改正後、年暮計画区域内のすべての建築物は階数2以上または延べ面積200㎡以上となります。都市計画区域外は、階数2以上、または延べ面積200㎡以上となりました。
参照:国土交通省 改正建築物省エネ法・建築基準法の施行時期について
参照:国土交通省 建築物再生可能エネルギー利用促進区域(建築物再エネ促進区域)について
福岡市の外壁塗装や屋根塗装の他、太陽光発電設置はOHANAにご相談ください

2025年4月1日から改正建築基準法が変わります。これまでお話ししてきた内容はごく一部で、他にも多くの内容が改正されることになりました。たとえば構造規制の合理化、二級建築士の業務独占範囲の見直しなどです。
リフォームをはじめ、太陽光発電の設置にも大きく関わる大幅な改正です。そのため、太陽光発電の設置を検討しているなら、この改正についても熟知している専門業者に任せなければなりません。
福岡市の地域密着おうちのかかりつけ医OHANAでは住まいの塗装工事をはじめとして、太陽光発電についてもくわしい専門スタッフが在籍しております。当然、改正建築基準法についても熟知しておりますのでご安心ください。
OHANAへのご相談はホームページの問い合わせフォームをご利用ください。その他、電話やメールでも受け付けております。
お問い合わせ・お申し込みはこちら!
日本の住宅は他の先進国に比べ住宅の耐久年数が
著しく低いと言われております。
特に、お家の防水に関しては定期的なメンテナンスが必要です。
屋根・外壁の塗り替え工事のご相談はオハナへお任せください!!
『オハナ』とは、ハワイ語で家族・仲間という意味です。
家族のように親身にご対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください!